検診でひっかかった。
園の先生から「専門機関を勧めます」と言われた。
他の子と比べて、発達の差をはっきり感じた。
わかっているつもりだった。
でも、「障害かもしれません」という言葉が胸に刺さって、そこから先の言葉が入ってこなかった。
そんな声を、よくネット上で見かけます。
「ちゃんと受け止めなきゃ」
「この子のために強くならなきゃ」
「私が変わらなきゃいけない」
そう思えば思うほど、心がしんどくなる。
・障害という言葉を検索しては、落ち込む
・SNSで同じような子を探しては、不安になる
・誰かに相談しても、納得できない
頭では理解していても、
“感情が追いつかない”ことって、あるかと思います。
私たちは、音楽療法士という立場で、発達に凸凹のある子どもたちと関わっています。
そこで感じるのは――
「この子は何ができないか」ではなく、
「この子は今、どんなふうに世界を感じているか」に目を向けることの大切さ。
診断名や成長の目安よりも、その子が音に反応したり、ふと笑ったりする“今の瞬間”に、その子らしさがにじみ出ることがあります。
音楽療法は、演奏の練習でも、才能を伸ばす場でもありません。
・声にならない音
・視線の動き
・リズムへの反応
・音に合わせた小さな動き
こうした言葉にならない「サイン」を、音の中で一緒に見つけていく時間です。
「障害を受け入れる」なんて大きなことじゃなくていい。
まずは“今ここにいる子ども”に、素直に触れる時間を持ってみませんか?
親であることと、専門家に向き合うこと。
その間で、心が板ばさみになるような気持ち。
痛いほど分かります。
音は、そんな時にそっと寄り添ってくれる存在です。
音は、何も判断しません。
正しいかどうかも、問いません。
でも、音を通して見えてくる子どもの表情が、親御さんの心をふっとゆるめてくれることがあると、私は感じます。
「障害があるかもしれない」
「でも、まだ受け止めきれていない」
その状態のままで、どうぞいらしてください。
音楽療法の場は、何かを“決める”場所ではありません。
ただ、今のお子さんがどんなふうに感じて、反応して、世界とつながっているのか――
それを、音とともに一緒に感じる場所です。
いつか“受け入れられた”と感じる日が来るかもしれません。
来ないかもしれません。
でも、そのどちらでもいい。
あなたとお子さんの今の姿を、否定しない場所が、ここにあります。
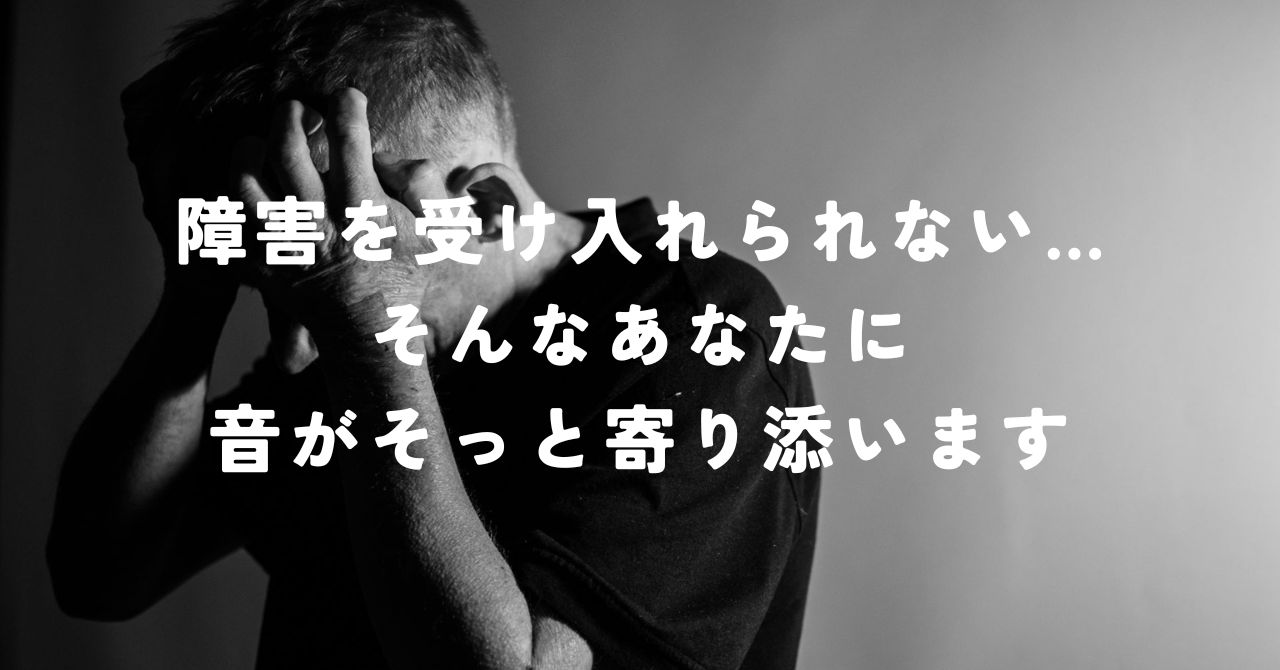



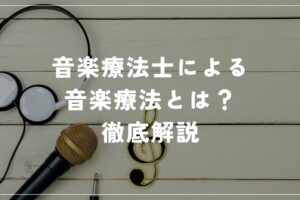








最近のコメント