「友だちを叩いてしまった」
「急に突き飛ばしてしまう」
「弟や妹を傷つけてしまうのではと心配」
子どもが他の子を傷つけてしまう「他害」の行動は、親御さんにとって非常につらい問題です。
理解してもらえず、責められるような視線に苦しむ日もあるかもしれません。
ですが、お子さんが“他害”をしてしまう背景には、必ず理由があります。
それは、「悪い子だから」でも、「しつけがなってないから」でもありません。
もしかすると、言葉にならない“何か”を、どうにかして伝えようとしているのかもしれないのです。
【子供の他害】「ことばにならない思い」が音楽に現れるかも
私たち音楽療法士は、子どもたちの行動や気持ちを音やリズムを通して観察し、関わる専門職です。
たとえば、こんなお子様がいたとします。
-
ことばは少ないけれど、音にだけは反応する
-
手が出てしまった直後、音を聴いて落ち着いた表情になる
-
楽器の音に合わせて、他人との関わりを受け入れていく
子どもたちは、“音のやりとり”の中で、少しずつ安心し、自分の内側を出す準備を整えていきます。
「他害」は“関わりたくない”ではなく、“どう関わっていいかわからない”というサインかも
他の子に近づきたいのに、うまく言えない。
不安や不快をうまく伝えられず、手が出てしまう。
子どもが他害行動をするのは、“関わりたいけど難しい”というSOSの形であることも多いです。
音楽療法の現場では、「なぜこの子は叩いてしまったのか」ではなく、「この子はどんなふうに今の気持ちを表現しているのか」に注目することがあります。
【子供の他害】安心できる場で、自分の気持ちを“音”で表現する
音楽療法では、叱られることも、正解・不正解もありません。
大きな音、小さな音、速いテンポ、ゆっくりしたリズム。
子どもが音楽療法の中で「安心できる表現」を見つけることで、少しずつ他者との関係にも変化が生まれてくることがあります。
そしてその過程で、子どもが自分でも知らなかった感情に気づくこともあると私は考えています。
「他害」を責めるよりも、その奥にある気持ちに目を向けてみる
「また叩いてしまった」
「どうしたらやめさせられるのか」
そう思ってしまうのは当然のことです。
でも同時に、その子なりの“伝え方”を見つける手助けがあれば、他害の頻度や質が少しずつ変わっていくこともあります。
音楽という“ことばじゃない世界”は、「今、何が起きているのか」を探るヒントになることがあります。



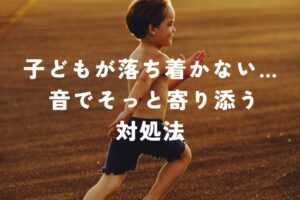



最近のコメント