このブログを運用している中で、山ほど質問されたことは
「音楽療法のネタを教えてください」
ということ。
この質問、前々から私のブログにもよく届いていた質問でして、多くの方が音楽療法の活動ネタに頭を抱えているんだなと日々感じます。
私もまだ音楽療法士としてデビューしたばかりの頃は、音楽療法のネタ本を片っ端から読み倒して真似したり、
リトミック活動ネタが書かれた本も合わせて読んだりととにかくありとあらゆる音楽活動のネタが書かれている本を読んでは真似ていましたが、最近はそのような本は「真似る」ために読むのではなく「参考」にするために読む程度に変わり今では私の音楽療法活動は、クライアント一人一人異なるほぼオリジナルな活動を行っています。
なぜ、ネタ本に頼りまくっていた私が、自分で活動内容を考えるようになったのか。
それは、子供たちに関する情報を学びに学んだことと、目標設定を徹底的に見直しブラッシュアップしてきたから
と感じております。
具体的にどのようなことかというと、私は音楽療法士としてデビューした頃、アセスメントの自信が全くありませんでした。
音楽療法士として稼動する上で、自閉症などの発達障害のお子様や様々な疾患について学んだり、認知症と言っても、アルツハイマーやレビー小体型なのか、その違いを学んだりしても、実際にその障害や診断名のあるクライアントを目の前にすると自閉症と言っても100人いたら100通りだし、全然本に書いている活動ネタをやっても自分が思い描いていたようにできないということが続いて「わたし、アセスメントがうまくできないなぁ…」と頭を抱えていました。
そんなとき、とあるご縁から民間で個別療育を行なっている方と知り合うことができ、その方からアセスメントについて徹底的に個別指導を受けることができました。
それと同時に大学院で音楽療法の修士取得を目指して、本格的に音楽療法の勉強をしていました。
この二つを同時に行ったことで私が行き着いたところは目標設定を徹底的に行うということでした。
もう音楽療法をしていたら当たり前の当たり前すぎて当たり前で申し訳ない話なんですが、とにかく大学院に行ってからこの目標設定に関してめちゃくちゃ鍛えられたんですよね。
また同時に、個別療育を行っている方からも目標設定にするにあたりどうしてその目標設定を立てたのかをぼっこぼこにしごかれたので一時「目標・目的」という文字を見ると震えが起き
大学院の人にも、個別療育の人にも、クライアントにも「会いたくて 震える」現象の真逆の事態が起きたのですが、(なんて冗談です)
冗談はさておき、そこまで徹底して目標設定とたくさんの事例などを学ぶことで何を音楽療法でサポートしていけば、引き出していけばが見えるようになってきました。
もちろんまだまだだけど。
例えば、音楽療法を受けられるお子様の多くはいわゆる問題行動という世間的には困った行動をとってしまうことがあります。
お友達と遊んでいるときに「貸して」が言えず無理やりおもちゃを取って喧嘩になってトラブルが多いというケースがあったとします。
このとき、昔の私は【「貸して」と言えるようにする】という目標を立ててたと思います。
この目標に関して、悪いとかそういうことを言いたいわけではありません。
大切なのは、もう一歩踏み込んでそもそもこの子はなぜ「貸して」が言えずに無理やりおもちゃをとってしまうことが多いのかを考えなくてはなりません。
もしかしたら、視覚優位で目に入ったものにはすぐに手を伸ばしてしまうのかもしれない。
そのとき体幹が弱くて日頃から寝っ転がって遊んでいることが多いため、視覚に入ってきたものを寝ながら奪うことが多い。
もしくはボディイメージが乏しく、どこまで自分の腕が届くのか、力加減ができなかったりして無理やり力づくでとっているかもしれません。
日常を見ていてそのような様子があったら、「貸して」と言えるようになる前にボディイメージを育てるような活動をすることが先に求められている場合があるかもしれません。
ボディイメージを育てるためには、感覚統合でいうところの触覚、前庭覚、固有覚をバランスよく育てる必要があります。
その子が触覚系に何かトラブルがあったら、モンテッソーリの遊び袋活動がいいかもしれない。
そこにオリジナルで「な〜にがあっるかな な〜にがあっるかな?」と歌ってみると楽しみながら活動ができるかもしれない。
お子様によってはおしくらまんじゅう遊びが必要な感覚かもしれないし、トランポリンで飛ぶことが必要かもしれない。
トランポリンを飛んでいるジャンプに合わせて飛ぶことで今自分がどんなテンポで飛んでいるのかが聴覚からもわかりやすくなるかもしれない。
このように何個も何個も「もしかしたら」という例を出しては目標を考えていくと、やるべきことというのが自然に見えてきませんか?
ネタはあくまでもアセスメントと目標の延長線上にあるものです。
その子自信が困っていること、その子親御さんのような周りの人が困っていることは何かを知りながら、原因は何かを考えると、目標が見え、そしてその結果活動内容につながると
私は考えています。
…とまぁ偉そうに言ってますが、そんな私も急にこんなふうにできるようになったわけじゃないですし、どうしたらいいかわからないときもあります。
チャレンジしては思うようにいかなかった活動もこれまで五万とあります。
そんなときは、SV(スーパーバイズ)を受けて意見をもらったり、様々な発達やネタ本を読んで知恵を借りたりしています。
人生生きている限り一生勉強の音楽療法。
もし今、あなたがネタに困っているようでしたらすぐに思い描いたような活動にしようと思わず、まずは改めてアセスメントをし直すような感覚で網一度クライアントをバイアスを外して観察して、その原因は何かを踏まえて目標、目的を考えてみると自然と活動内容が見えてくるかと思いますよ‼︎
音楽療法はクリエイティブな仕事だと思っております。
お互い頑張りましょう♫
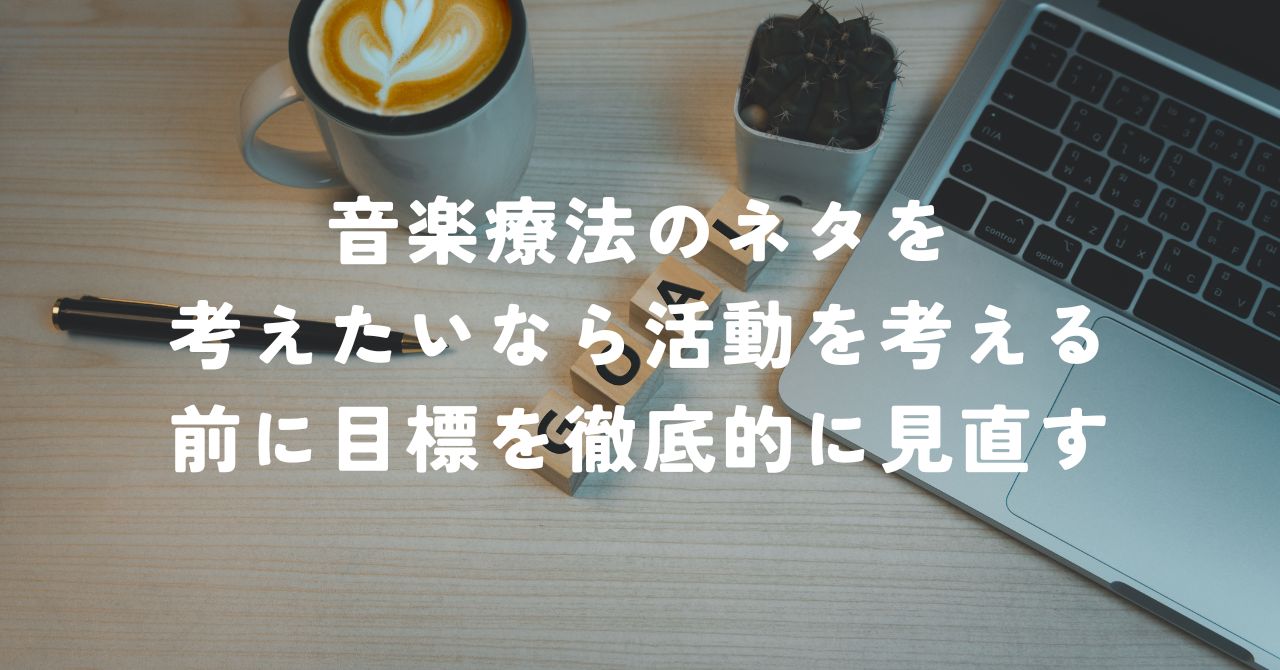
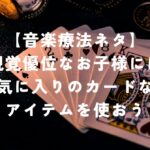







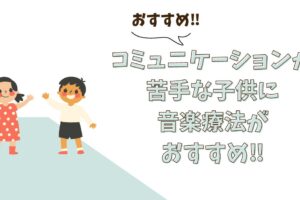
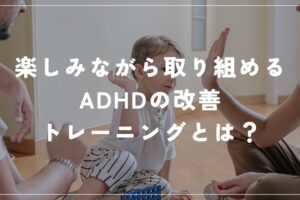


最近のコメント