「靴下を履くのを嫌がる」
「音にびっくりして泣き出す」
「においや光に敏感すぎて外出が大変」
一見わがままに見られたり、「育て方のせい」と誤解されたり…
でも実は、感覚が過敏な子どもたちが抱えているのは、“見えないつらさ”だったりします。
「うちの子だけなんじゃ…」と感じてしまう親御さんも少なくないのではないでしょうか?
感覚過敏の子供には「安心できる環境」が必要
感覚過敏の子供たちは、
音、光、触覚、においなど、五感のどこかに「過敏さ」を抱えています。
-
騒がしい音に圧倒されて、何も手につかない
-
服のタグのチクチクで、パニックになってしまう
-
突然のにおいや風の刺激で、固まってしまう
こうした反応はその子の「感じ方」そのもので、本人にもコントロールできないことが多いのです。
だからこそ、必要なのは「がんばらせること」ではなく、安心して過ごせる関わり方だと私は考えています。
音楽療法は、「感覚をやさしく整える時間」にもなる
私たち音楽療法士は、子どもの感覚の特性を見ながら、その子にとっての音楽という“安心の素材”を使って関わります。
たとえば…
-
やさしいテンポや音色の音で、心を落ち着ける
-
自分で音を鳴らすことで、感覚をコントロールする経験を積む
-
音の予測ができる環境で、安心してやりとりを楽しめる
- 適切な楽器で関わる
音楽療法の現場では、その子にとっての「この音なら心地いい」という“その子だけの安心”を一緒に見つけていきます。
「刺激が少なく、でもしっかり届く」それが“音の支援”
感覚過敏の子には、「刺激の強さ」ではなく「安心できる刺激」が必要だと考えています。
音楽は、
-
触らなくても関われる
-
自分のペースで楽しめる
-
不快な刺激を避けながらも“つながる”手段になる
そんなやさしい感覚の世界をつくることができるツールの一つです。
「できることを増やす」のではなく、「安心できる時間をつくる」
音楽療法では、「〇〇ができるようになる」ことだけをゴールにしません。
まず大事にするのは、その子が安心していられること。
そこから、少しずつ「心を開いてもいいかな」「やってみようかな」が生まれてきます。
感覚がつらくてがんばれない時こそ、
がんばらなくていい場所=音楽療法の空間が力になります。









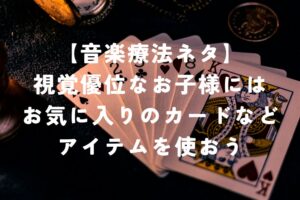



最近のコメント