音楽療法を受けられるお子様の中には発達障害のあるお子様もいらっしゃいますが、その中に視覚優位のお子様に出くわすことがあります。
視覚優位とは読んで字の如く、視覚が優位に働くことです。
音楽療法では音楽を使用するので、聴覚優位のお子様の方が有利なのかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
視覚優位のお子様に対しては、私はよく、その子が興味を持てるアイテムを使ってカードなどを使用します。
例えば、クライアントのお子様が車が好きな場合、さまざまな車のカードを作ってその子の目の前で提示します。
そして、一緒にそのカードを使ってその子だけの【車のカードを走らせるオリジナルソング】を歌います。
この時、私が作曲する時のポイントとして、音楽の長さを8小節ほどの短いものにすることです。
その理由として、短い曲を繰り返すことでお子様に覚えてもらいやすくすることがあります。
またそのほかに、短い曲の中で変化をつけ、お子様とコミュニケーションにつながるようにやりとりを楽しみます。
例えば、8小節の歌を覚えてきた頃合いで歌を歌うのを途中でやめると、お子様がこちらをみてくるかもしれません。
目線があって、間合いを見てからまた歌い始めると、お子様は歌が始まったことで喜ぶかもしれません。
そして喜んだ後、再び歌を歌うのを途中でやめると、またまたお子様はセラピストの顔をみてくるかもしれません。
もうこのやりとりを想像しただけで、言葉はなくても十分コミュニケーションができていると思いませんか?
これは音楽療法士の職業病あるあるなのかもしれませんが、私がまだ経験が浅い頃、音楽療法活動では楽器をメインに使わないといけない思い込みが強くありました。
しかし、保育士の知り合いにあい、保育士の方がパネルシアターなどを使っている様子を見て、「音楽療法でもこのようなアイテムを使ったらどんどんいろんな可能性が引き出せるのではないか?」と思ったのです。
視覚優位のお子様と音楽療法活動でコミュニケーションを図りたいと思ったら、ぜひそのクライアントのお気に入りのアイテムなどをカードにしたりして、一緒にやりとりをする時間を設けてみてはいかがでしょうか?
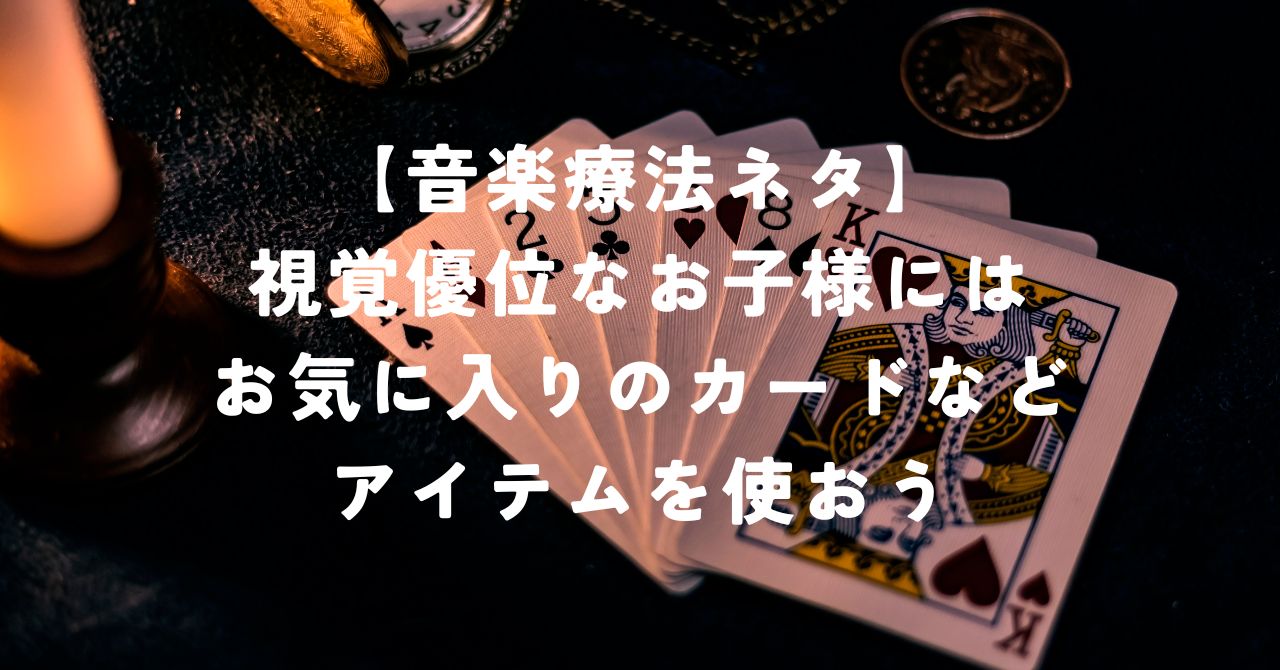
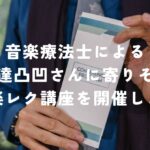
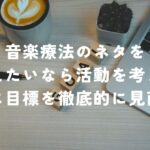




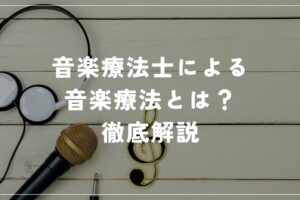


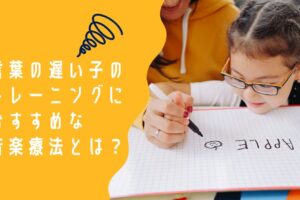


最近のコメント