私は保育園の先生と一緒にお仕事をすることがあるのですが、時折
「保育園でリトミック活動をしている時に離席してしまう子がいて困っている」
という相談を受けることがあります。
保育園や幼稚園、音楽教室などでリトミック活動を行っている途中、先生が話している時に立ち上がってしまったり、みんなで楽器を鳴らす時間にも関わらず、楽器を投げて部屋から逃げようとするお子様、時折出くわすことがあります。
音楽療法でも活動中に離席してしまう子をたくさん見かけますが、一言で「離席」と言っても離席する理由は様々です。
例えば、視覚優位なお子様の場合、先生が話している後ろで何か物陰が動いたのに気づいてしまって思わず立ち上がってしまったのかもしれない。
もしかすると、体幹が弱かったり整っていないことが理由で、椅子に数分間座ることが難しいのかもしれない。
どちらも結果は同じ「離席」につながっていますが、その離席を解決するためのアプローチは、原因が異なるため違ってきます。
最初に紹介した視覚優位なことが理由で離席をしてしまう場合、まずは徹底的に視覚的刺激をなくすように、リトミックを行う環境設定を見直しましょう。
よくあるのが、窓から見える車の動きに視線が向いてしまい走り出してしまうことがあるので、そのような場合はカーテンなどをするといいでしょう。
また、姿勢維持などができずに椅子に座っていられない場合は、具体的に姿勢保持に必要な何ができて何ができないのかをしっかり見極めることが大切です。
例えば、発達がゆっくりなお子様の中には、耳の中にある三半規管の中にある重力を感じる部分が鈍いため、重力に負けてしまい姿勢を保持することができないという場合があります。
この場合は、意図的に揺れる活動をすることで感覚刺激をすると効果が見られる場合があります。
これをリトミック活動で行う場合は、子供にブランケットの上に乗ってもらい、ゆっくり左右に揺らす動きに合わせて音楽をつけるといいでしょう。
この活動では、三半規管に重力加速度の刺激を入れるという目的以外にも、一人一人順番に行うことで順番を待つという活動にも繋がります。
また、この時使用する曲を8小節ほどの短い曲を使用することで、順番が待つのが苦手なお子様も短時間で見通しが持ちやすい中、待つ練習をすることにも繋がります。
また、発達障害のあるお子様の中にはコミュニケーションを取ることが苦手なお子様もいらっしゃいます。
もし、このブランケット遊びが好きでまたやりたいというお子様がいた場合、タッチをする、カードを渡して「もう一回」お願いすることを要求するなどの自分の意思を相手に伝えるコミュニケーションの練習の機会にもつながります。
ここでお伝えしたいことは、「離席」と一言に言っても離席する理由をしっかりと見極めない限り、適切な音楽活動というのが見えてこない場合があります。
よくよく見ていると、必ずその子が離席する理由やタイミングは見えてきます。
まずはよく観察することで、その理由を見極めてから、音楽を用いて何ができるのかを考えてみるといいでしょう。
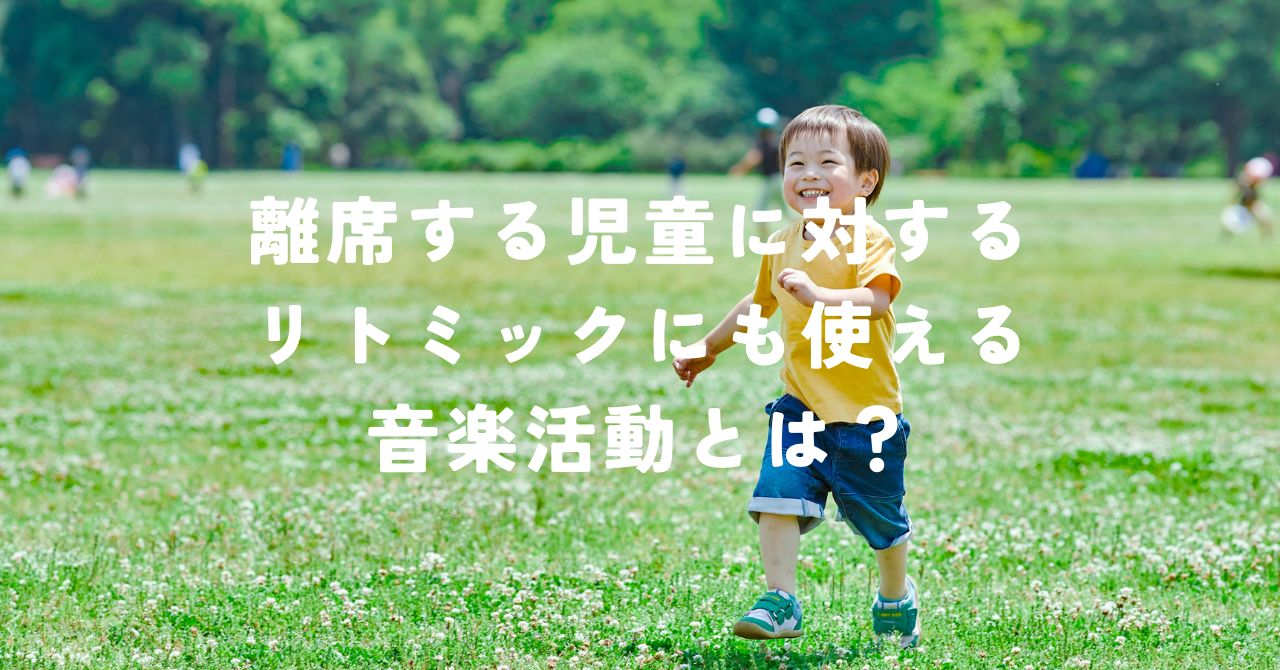
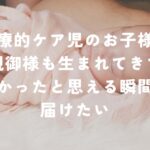


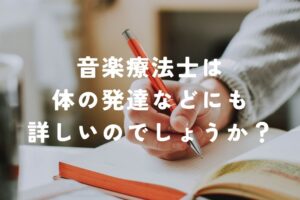



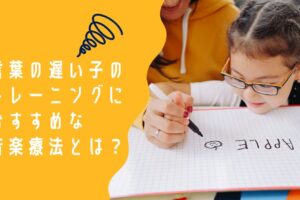




最近のコメント