発達がゆっくりなお子様や発達が凸凹しているお子様の中には、切り替えが難しいというお子様がいます。
例えば、遊びの時間が終わりに近づいてもなかなか片付けをしない。
出かける時間を前もって伝えておいても、なかなか出かける準備をしようとしない。
このようなことが積み重なると、親として時に感情的になってしまうこと、ありますよね。
私も3歳児の母でありますが、思うようにスケジュールが進まないことが続くと私自身も子供にキレてしまうこと、あります。
ですが、なるべくそうならないようにいつも心がけていることは、心に少しの余裕を持って子供に共感する時間や心を持つことです。
これは発達ゆっくりさんや発達凸凹さんに限らず、世の中ほとんどのお子様に言える話ですが、誰だって楽しいことをしているときに、「もう終わりだよ」と言われて嬉しくなる人はいません。
てゆーかむしろ癇に障ります。
私だって、大好きなときメモGS4の七ツ森実くんとのデートの途中で「もう終わり」と言われたら、「終わりたくない!」「まだゲームさせて!」と大絶叫します。
また、視点を変えると、切り替えて欲しいなと思うのはぶっちゃけ大人都合の話です。
あと5分で出かけてくれると助かる。
出かける前に片付けもしてくれた状態で出かけられると嬉しい。
これらは全部大人目線の話になります。
そんな大人都合に合わせてくれる子供がいる方が、むしろ超珍しいと思っちゃうのが私の考えです。
まだ人生3年とかそこらの子供が、楽しくて遊びを辞めたくなくて切り替えられないのは自然なことだと自分自身子育てしていてもとても感じます。
そんな子供に対して、私が音楽療法で大切にしていることは、共感する気持ちを大切にすることです。
切り替えが難しいお子様というのは、それだけやりたい遊びやものが目の前にあるということ。
最近世の中では、大人向けに「やりたいことを探そう」ということがテーマになっているものがたくさんありますが、そんな大人から見たら出かけたくないほどにやりたいことがあるってものすごく羨ましい話です。
ちょっと話はそれましたが、私の個別音楽療法では場合によってはその子のやりたいことをやりたいだけさせるケースもあります。
例えば、ハンドドラムという太鼓があるのですが、これをくるくる回すのは好きなお子様がいたとしたら、その子がやりたいだけハンドドラムをコロコロ転がす活動を目一杯遊ぶことをします。
※ハンドドラムってこんなドラムです↓
長い時は20分も30分も同じ活動をすることがありますが、一見長時間とも思える時間取り組むのかというと、何より大切なのは子供自身が「やりきった」と感じる、その感じ切る心を育むことだと思うからです。
もちろん、切り替えが難しいお子様全員に同じ対応をするわけではないですが、やりきったという達成感を感じる機会を作るとスムーズに切り替えができるお子様の場合はこのような手法を取るケースがあります。
音楽療法を学んでいく中で、「クライアントを信じる」という言葉に出くわすことがあります。
音楽療法に限らず、お子様を信じることで、この切り替えがある日苦手から得意に変わることはあります。
もし今、お子様が切り替えるのが苦手という場合は、お子様自身で切り替えられる力を育むよう、大人側が待つ余裕を持つことが大切だと私は考えております。
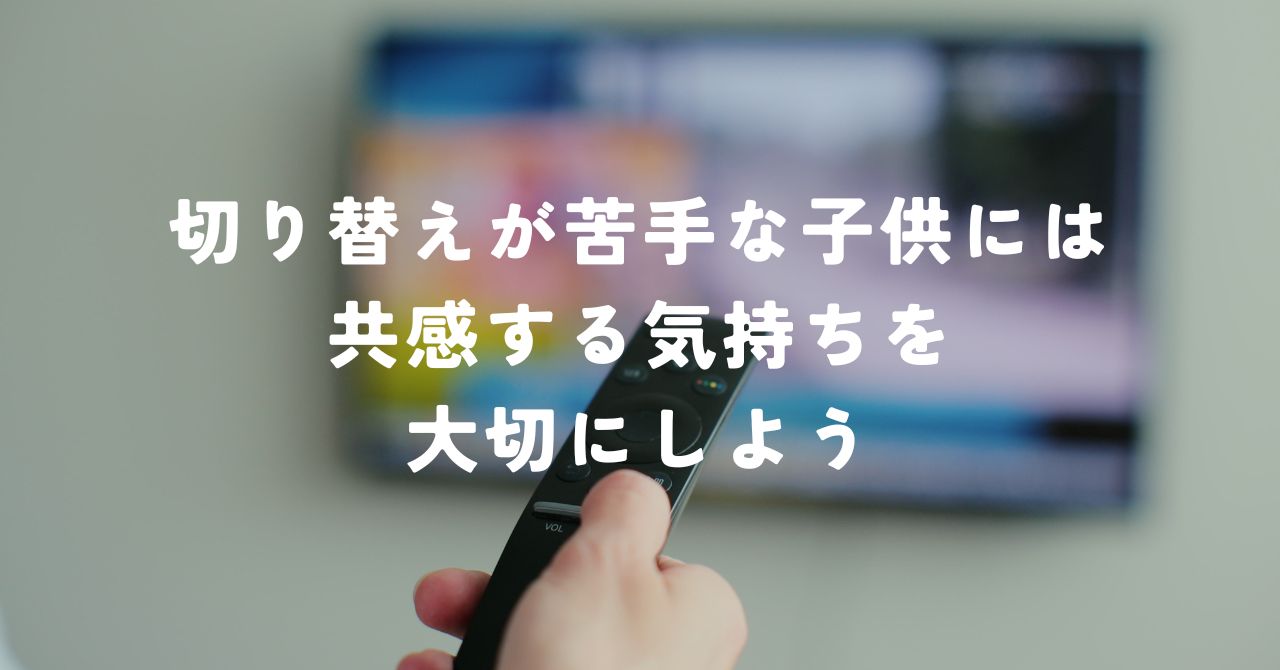




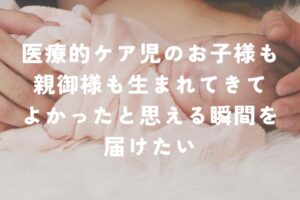







最近のコメント