発達がゆっくりなお子様の中には、集団行動が苦手なお子様もいらっしゃいます。
しかし、「集団行動が苦手な子供」と一言でまとめても、苦手な理由は100人いれば100通り。
集団行動が苦手でも、その理由は多岐にわたります。
今回は、もしかすると集団行動が苦手なお子様の中には、情報の処理速度がゆっくりなお子様なのかもしれないという例についてお話をしていきます。
例えば、幼稚園や保育園などでみんなでリトミックをしようとなったとき、ほとんどのお子様はみんなでわいわいきゃっきゃと先生の指示に従って行動をしていたとします。
その中で一人、集団から離れて先生をじっとみるものの、活動には積極的に参加しないお子様がいたとします。
そのような子を見ると、一見「なんでこの子はいつも離席してしまうんだろう」と思ってしまうかもしれません。
しかし、もしかするとその子は集団活動の様子をじっくりみて、「今入った何をする時間なのか」を先生を見ながらゆっくりと考えているのかもしれません。
このようなお子様はもしかすると、情報処理速度がゆっくりな傾向にあるのかもしれません。
お子様の情報処理速度は一人一人異なります。
一回見てすぐに理解できる子もいれば、繰り返し何度も見ることで理解できる子もいます。
もし、集団行動が苦手なお子様がこの情報処理速度がゆっくりなことが理由だとしたら、短い活動を繰り返し行うと集団行動に参加しやすい環境になると私は考えております。
例えば音楽療法の場面でしたら、8小節ほどの短い歌を用いて、何度も何度も同じ活動を繰り返すことを行います。
音楽療法を受けられるお子様の多くは、発達がゆっくりなお子様が多く、そのため繰り返しが有効になる場合があります。
子供は基本、同じことを繰り返し遊ぶことでさまざまなことを学び、吸収します。
そのため、発達がゆっくりな未就学児の音楽療法では、短い歌を繰り返し歌う活動というのを、よく取り入れられます。
具体例を挙げると、【大きなたいこ】という8小節でできた歌がありますが、この歌を通じて、何度も何度も「大きな太鼓」の歌詞で大きく太鼓を叩き、「小さな太鼓」の歌詞で太鼓を小さく鳴らして見せるという活動を行います。
お子様にもよりますが、場合によってこの繰り返しの活動を5分以上行うこともあります。
8小節の歌を5分以上も行うと聞くと、一見「そんなに繰り返しやって飽きちゃわない?」と思うかもしれませんが、情報処理速度がゆっくりなお子様にとってはそのくらい繰り返すことで理解につながりやすいケースもあります。
また、発達がゆっくりなお子様の中でも、5分ほど繰り返すことで理解につながりやすくなる場合があります。
もし、集団行動の時に遠くからじっと見ているけど行動しないでいる…そんな子は情報処理速度がゆっくりなのかも?と思って観察してみると、もしかすると適切な音楽活動が見つかるかもしれません。
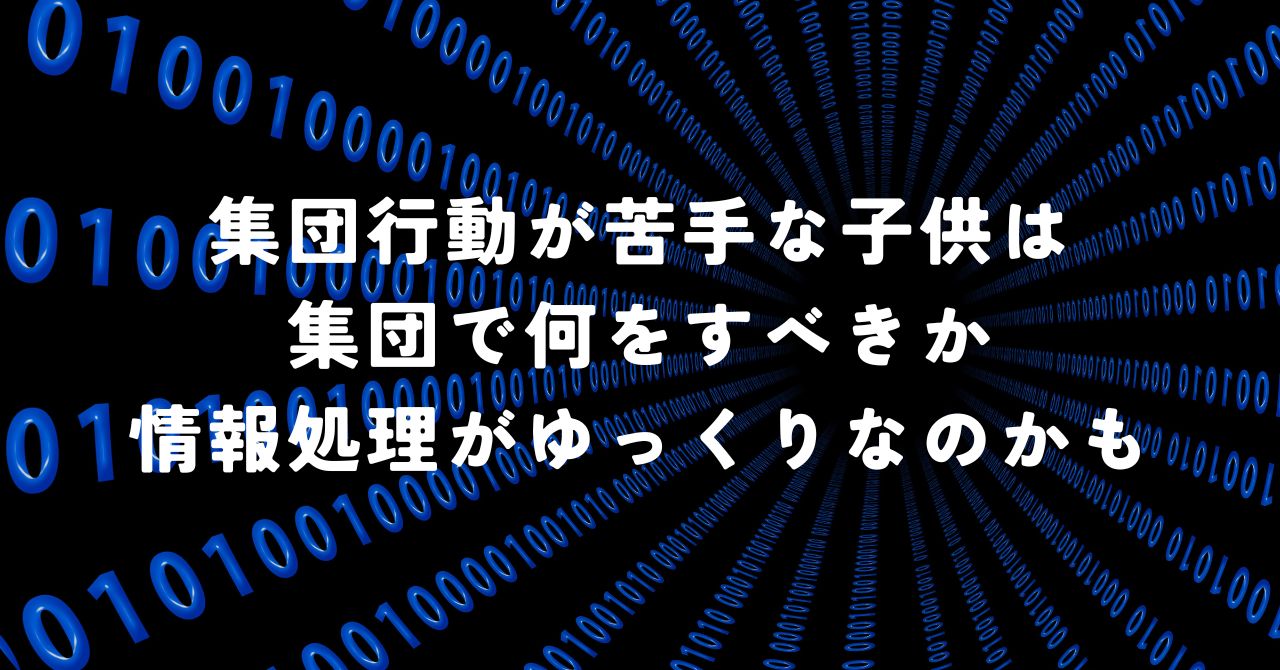

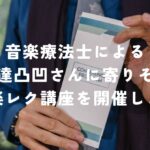










最近のコメント